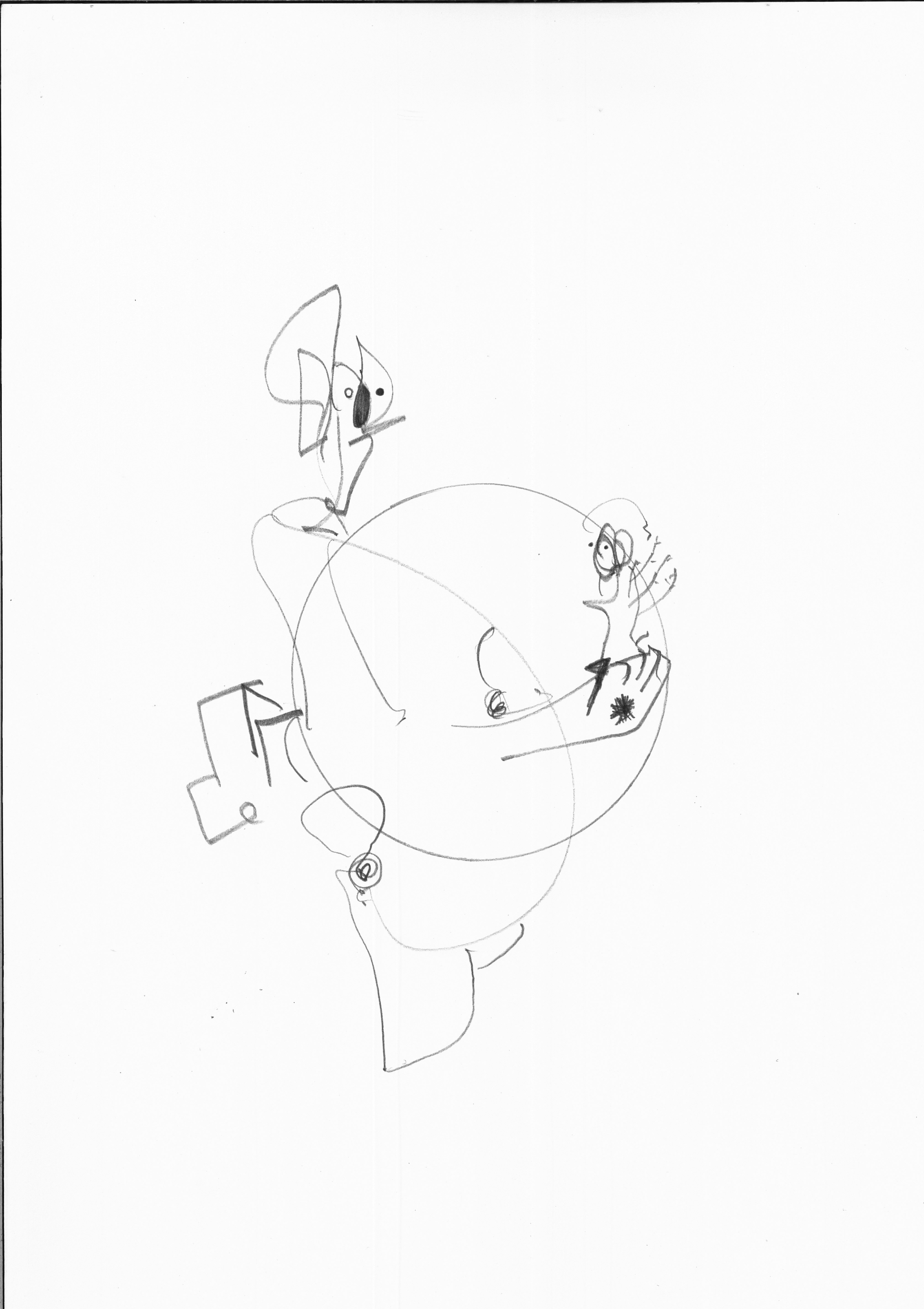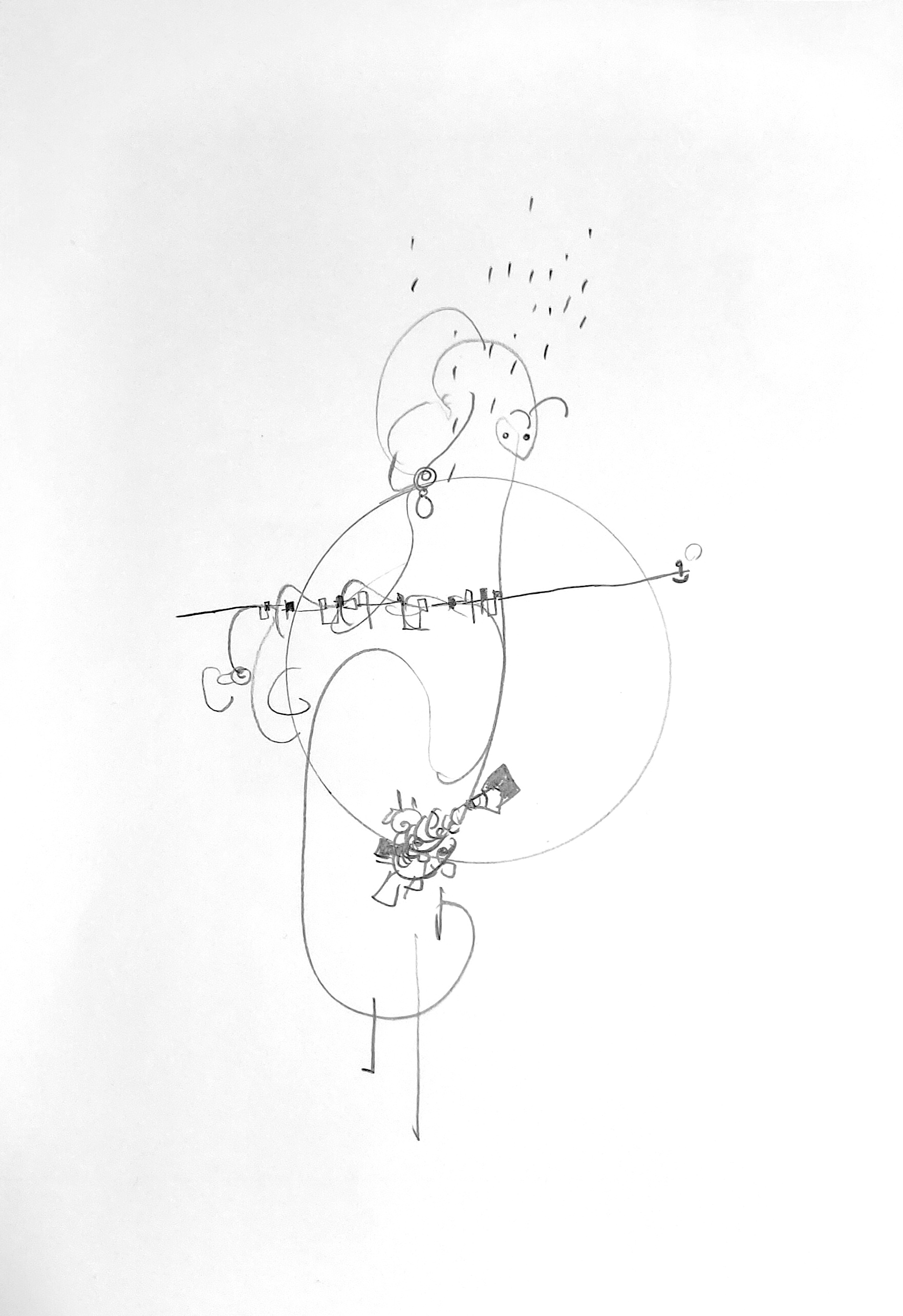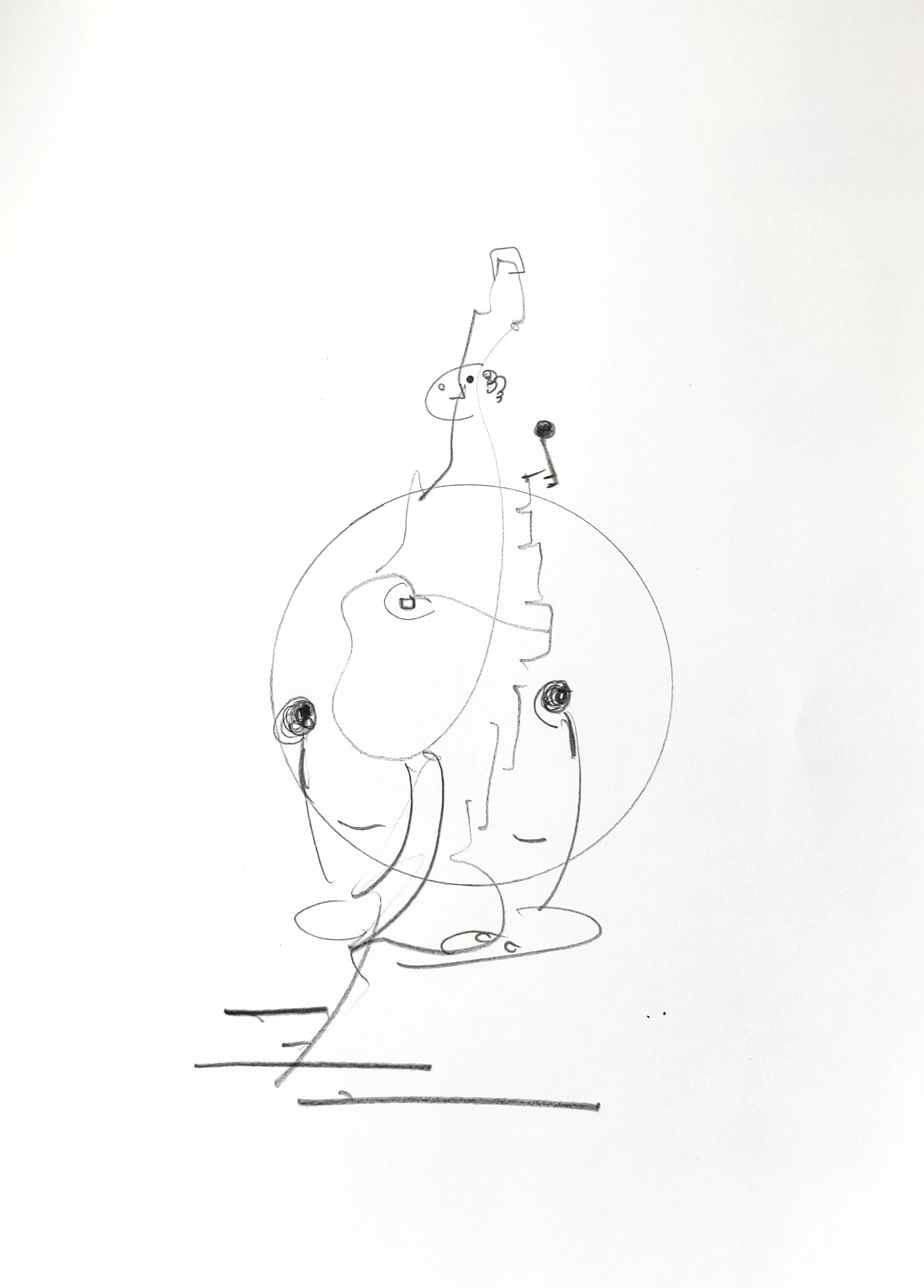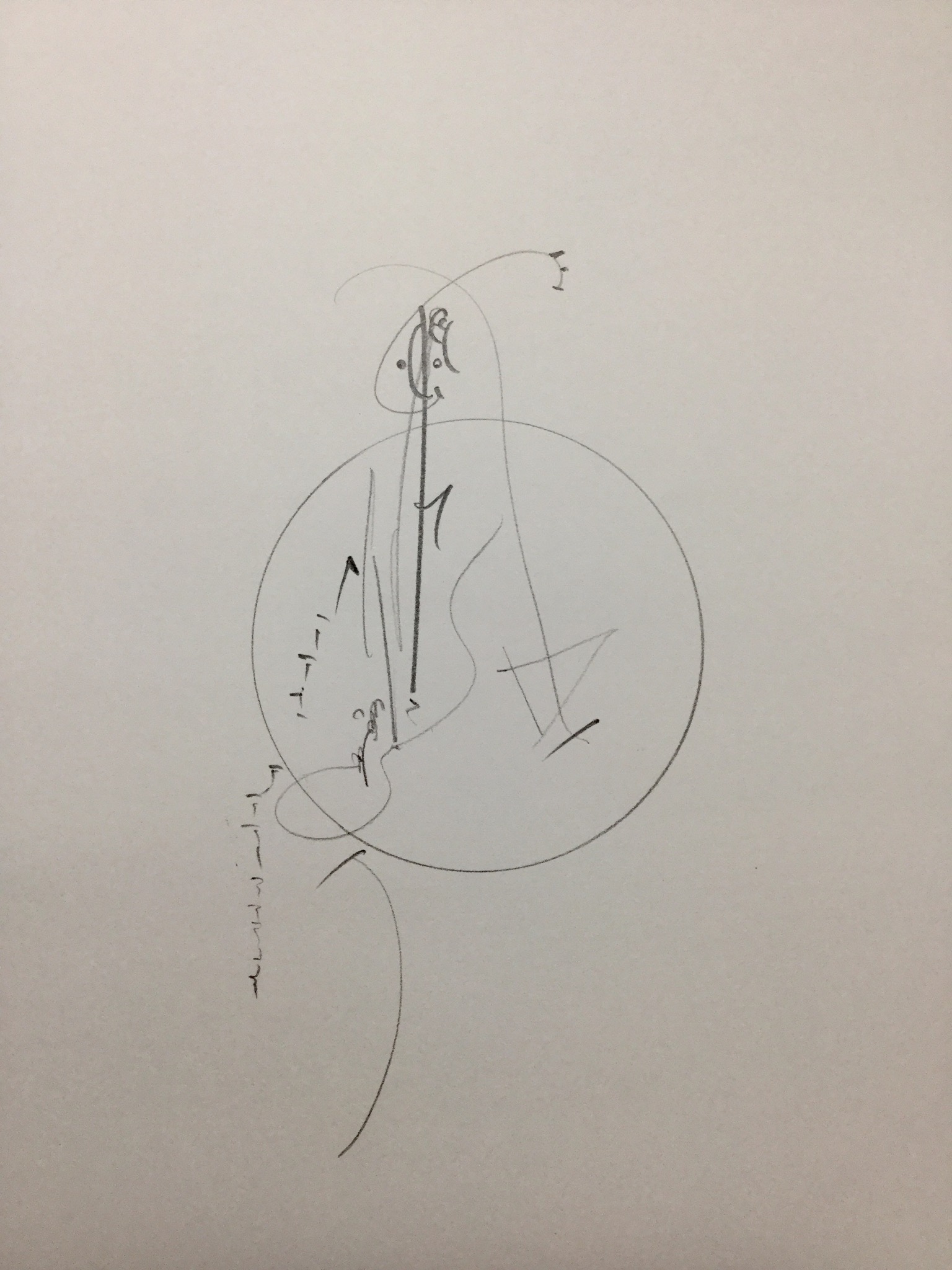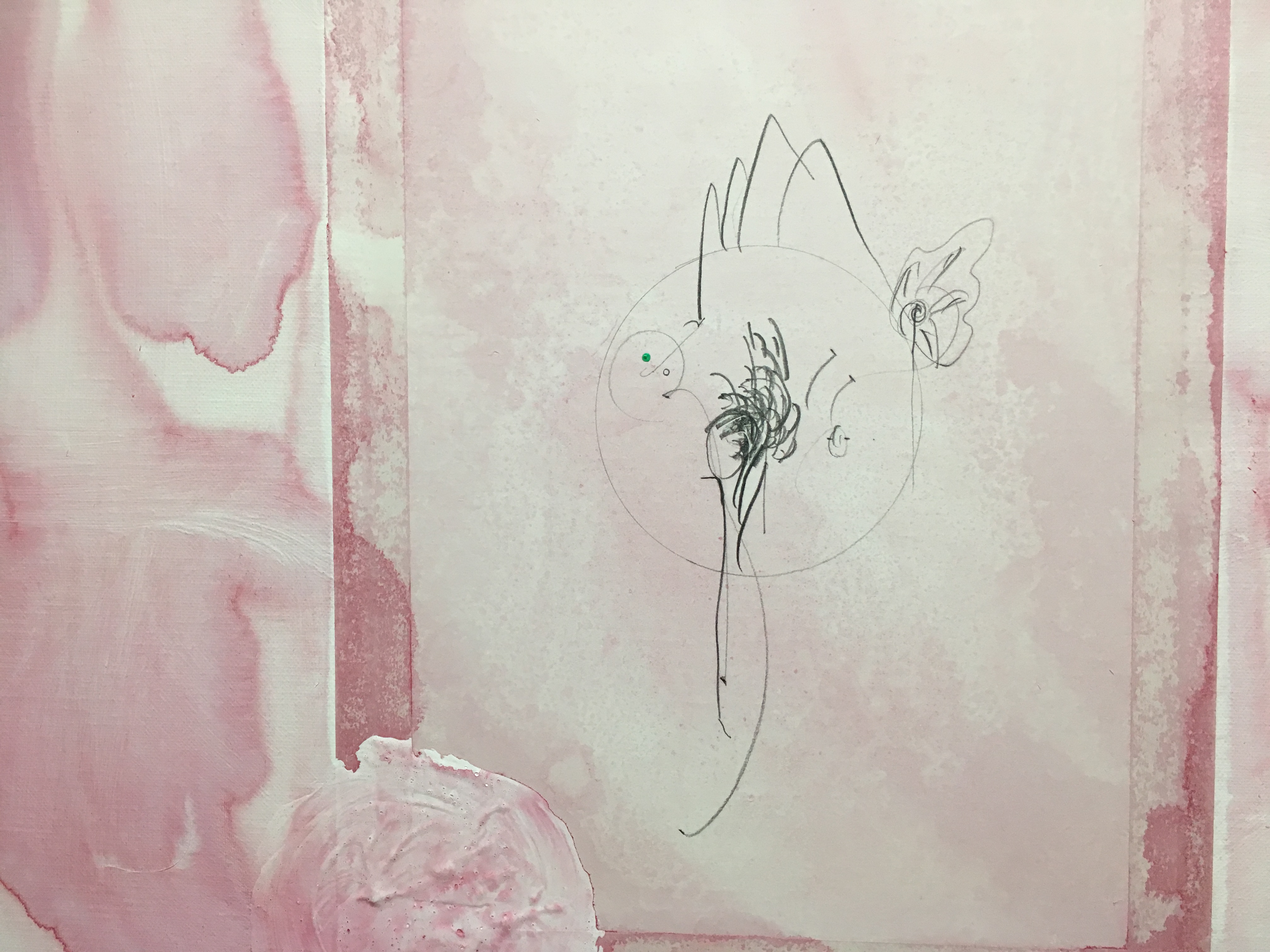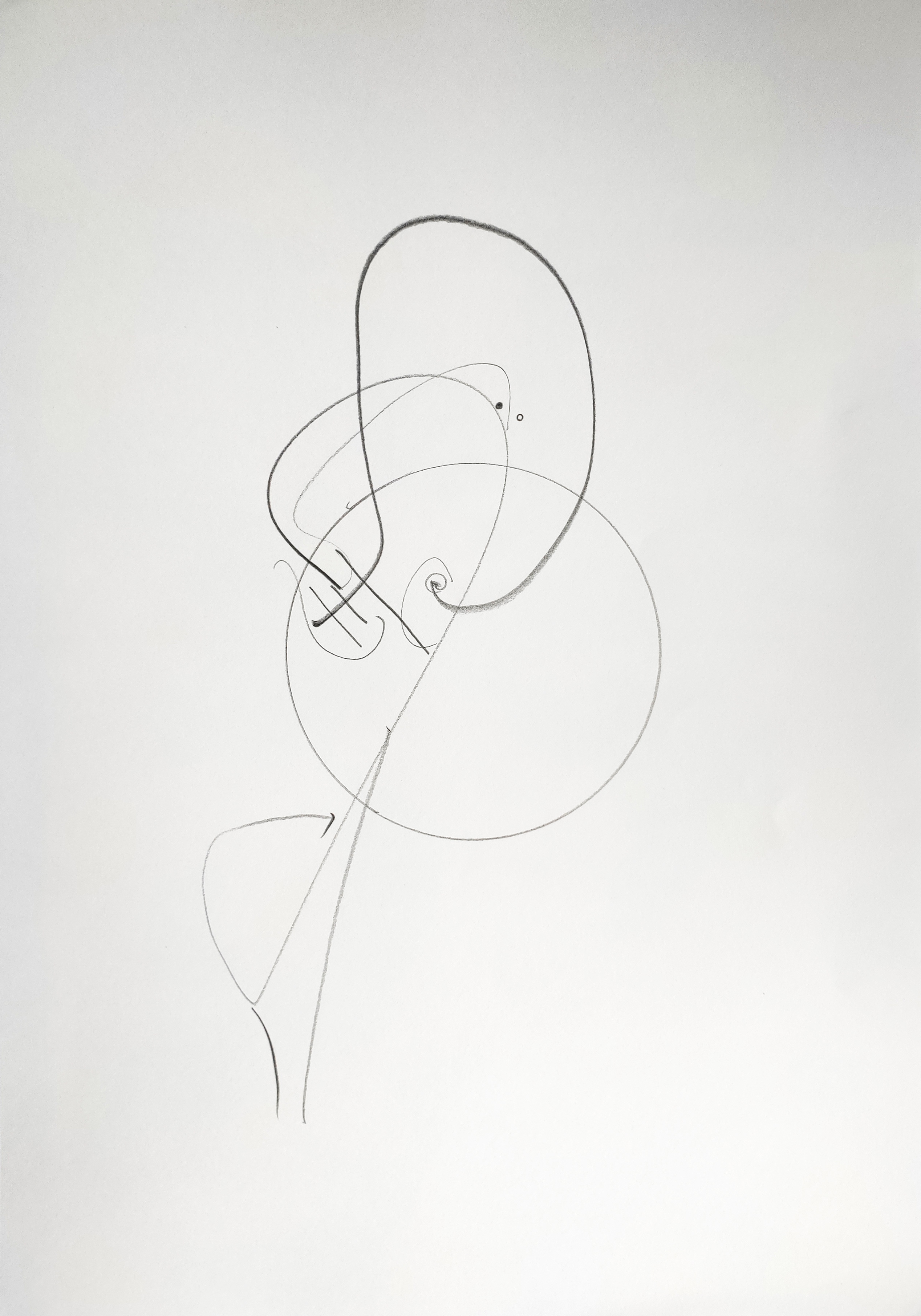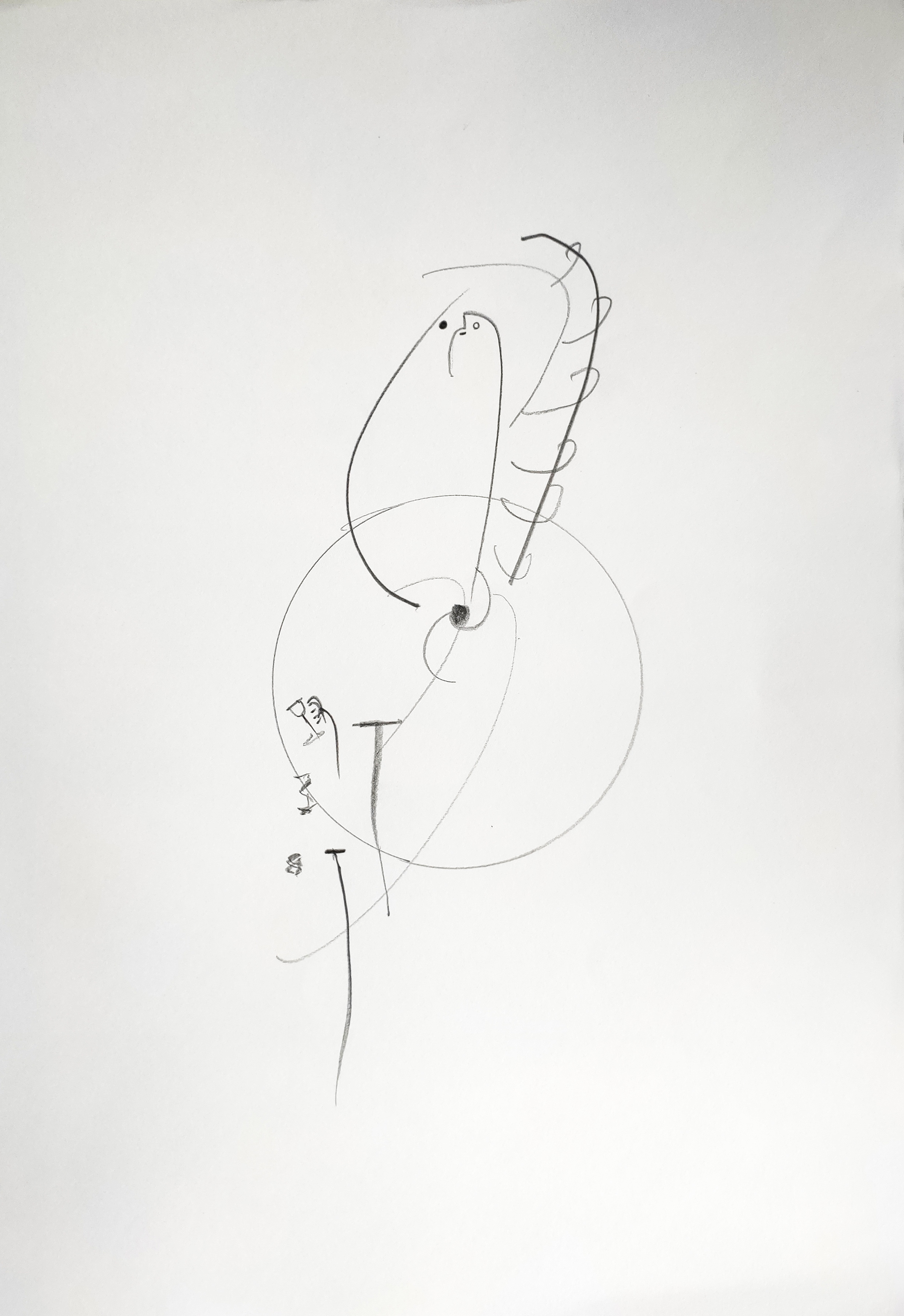自分の絵を見ながらはっきりと感じるのは、やはりここに描かれた奴らが”本当にいる”ということだ。それはもちろん普通の意味での”いる”とは違うし、これがただの絵だと言うことはわかっているのだが、それでもこうして絵を見ている間だけ、その間だけは確かにこいつらは”いる”のだ。恐らくこれは僕の思い違いか、絵画の神秘のどちらかだろう。”何かいる”ということが、絵画の神秘の根っこであるような気がする。
あわや雨
振り向けば羽
詩人と鍵
見えなかったものが見える
要素を剥ぎ取る
見るということ
見るということは、ひとつの謎を見つけるということだ。
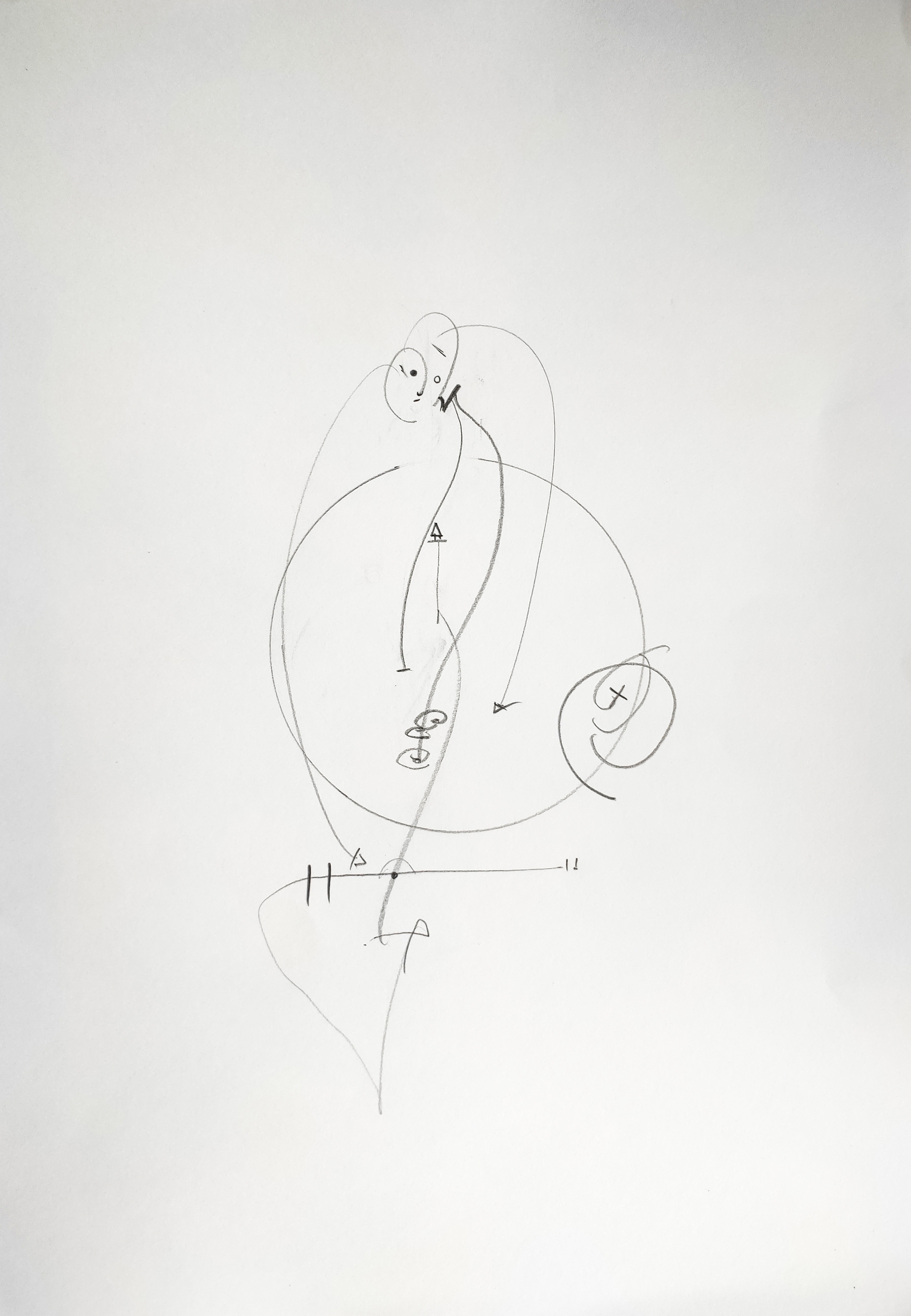
18/sept/2019
詩的言語と詩的な線
詩的言語とは、端的に言って、日常的言語の顛倒を基本とする言語である。例えば、詩人が「雪の始まりと終わり」と発する時、この表現は、それが日常的言語として機能する際には意味するであろう、単なる気象現象一般のみに志向しない。ある人にとっては、「閉塞と解放」であったり、「沈思と行動」であったり、もっと個人的な記憶に結びついた何かであったりするだろう。詩的言語は、我々の日常的言語が、漠とした了解によって保つ語とその意味するものの結びつきを断ち切る、もっと言えば作り直してしまう。この意味で顛倒である。
同様の現象が絵画においても起きているかもしれない。大胆に言ってしまえば、「詩的線とは、端的に言って、日常的線の顛倒を基本とする線である」となるだろうか。日常的線なるものを日常的言語と同じように理解することはできないが、要するにただの線でしかないような線と考えたい。単なる線の塊が、突如「絵」となる瞬間がある。もちろん線はただ線であるだけで造形要素として美しく、変質など全く意に介さないという立場もあるだろうが、何というかこの議論は、眼に見えているもの中に、眼には見えない何かが確かにいる、とどうしても思ってしまうような人に向けて書いているので、この際それは脇に退けてしまう。「眼には見えない何か」とは如何なるものか、本当にそんなものがいるのか、という問題については、それを確信してしまう人間の経験についてまず議論する必要があり、ここではまた別の問題となってしまうので、また別の機会に。
さて、単なる線を一本また一本と重ねていく内に、それが変質する瞬間がある。それはとどのつまり、語という我々の日常に属するものが、組み合わせかどの要因かは分からないが変質し、普段と違う振る舞いを始める、その瞬間とパラレルである。むしろ詩人は積極的にこの転覆を意図するだろうし、線描家が絶望的に線を重ねていくのも、彼にとってのこの希望を、視界の端に捉えながらであるかもしれない。
13/sept/2019
「酔いたまえ」
「酔いたまえ」
「常に酔っていなければならない。すべてはそこにある。それが唯一つの問題なのだ。君の肩をへし折り、地べたへと傾がせる、時間の恐るべき重荷を感じずにいるためには、休みなく酔っていなければならない。
しかしどんなものに?酒にか、詩か、徳にか、それは君の自由だ。ただ、酔いたまえ。
そして時折、宮殿のきざはしで、土手の緑の草の上で、君の部屋の陰鬱な孤独の中で、目覚め、酔いが衰え、消え失せてしまったならば、問いたまえ、風に、波に、星に、時計に、全ての逃れ行くものに、すべてのうめくものに、すべての流転するものに、すべての歌うものに、すべての語るものに、いま何時であるのかと。そうすれば風は、波は、星は、鳥は、時計は、君にこう答えるだろう。 《酩酊の時間だ!時間に責めさいなまれる奴隷になりたくなくば、酔いたまえ。酔いたまえ、絶え間なく!酒にか、詩か、徳にか、それは君の自由だ》。」
シャルル・ボードレール 『パリの憂愁』より
より軽やかに
より軽く、従ってより不条理に、つまりより真実に。ただしその軽さは、「ここに何かいる」という確信によって、最も深く、従って最も重い海底に錨をおろしていなければならない。